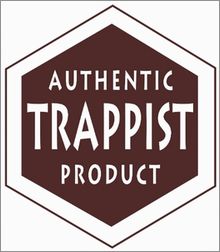Chimay Bleue
2025.08.08
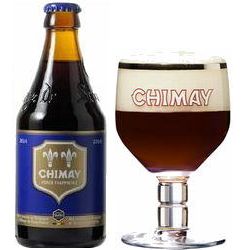
修道院が生んだ至高の一杯
『シメイ ブルー』は、ベルギー南部のスクールモン修道院で造られるトラピストビール(※)の代表格であり、世界中のビール愛好家から高い評価を受けるダーク・ストロング・エールです。トラピストビールとは、厳格な基準を満たした修道院で醸造される特別なビールであり、シメイはその中でも最も有名なブランドのひとつです。
⇒トラピストビール(※)
〇トラピストビールは、キリスト教カトリックの厳律シトー会(通称トラピスト会)の修道院で醸造される、特別な条件を満たしたビールです。単なるビールのスタイルではなく、宗教的・文化的背景を持つ「認証制度」に基づいた存在であり、世界でも限られた修道院のみが「トラピストビール」と名乗ることを許されています。
歴史的背景と起源
トラピスト会の起源は1098年、フランスのシトー修道院にさかのぼります。中世ヨーロッパでは安全な飲料水が乏しく、修道院では栄養価が高く保存性に優れたビールが造られるようになりました。修道士たちは巡礼者や貧しい人々にこのビールを振る舞い、信仰と慈善の精神を体現してきました。フランス革命や戦争による破壊を経て、19世紀以降に再興された修道院では、伝統的な醸造技術が確立され、現在のトラピストビールの礎が築かれました。
認証と条件
1997年に設立された「国際トラピスト協会(ITA)」は、以下の3つの厳格な条件を満たすビールにのみ「Authentic Trappist Product」の六角形ロゴマークの使用を認めています:
・ 修道院の敷地内で醸造されていること
・ 修道士が自ら醸造するか、監督していること
・ 収益は修道院の維持や慈善活動に充てられること
この認証は、品質と倫理性の両面を保証するものです。
特徴とスタイル
トラピストビールは上面発酵のエールで、瓶内二次発酵(再発酵)を行うため、熟成によって味わいが変化します。一般的にアルコール度数は高め(8〜11%)、風味は濃厚で複雑。フルーティーさやスパイシーさ、酵母由来の香りが特徴です。専用グラスは聖杯型が多く、香りを引き立てる設計になっています。現在、世界にトラピスト会修道院は約160ヵ所あり、そのうち9ヶ所でのみトラピストビールが生産されている(2025年時点)。
・ オルヴァル (ベルギー/オルヴァル修道院)
・ シメイ (ベルギー/スクールモン修道院)
・ ロシュフォール (ベルギー/サン・レミ修道院)
・ ウェストマール (ベルギー/聖心ノートルダム修道院)
・ ウエストフレテレン (ベルギー/シント・シクステュス修道院)
・ ラ・トラップ (オランダ/コニングスホーヴェン修道院)
・ ズンデルト (オランダ/アブダイ・マリア・トゥーフルフト修道院)
・ トレフォンターネ (イタリア/トレフォンターネ修道院)
・ ティント・メドウ(イギリス/ティント・メドウ修道院)
シメイ ブルーの最大の魅力は、濃厚で複雑な味わいにあります。グラスに注ぐと、深いマホガニー色とクリーミーな泡が立ち上がり、プラムやレーズン、イチジクなどのドライフルーツを思わせる芳醇な香りが広がります。口に含むと、キャラメルやトフィーの甘み、スパイスのニュアンス、そしてほのかなアルコールの温かみが調和し、長く続く余韻を楽しめます。アルコール度数は9%と高めですが、バランスが良く、重厚ながらも飲みやすい仕上がりです。
さらに、瓶内二次発酵によって熟成が進むため、数年寝かせることで味わいがまろやかに変化し、より深みのある風味を楽しむことができます。食後酒としても優れており、濃厚なチーズやチョコレート系のデザートとのペアリングは格別です。
「シメイ ブルー」は、ただのビールではなく、修道士たちの祈りと技術が込められた文化的な逸品。静かな夜にじっくりと味わいたい、心を満たす一杯です。
■飲み方あれこれ!!
おすすめ温度:10〜14℃
シメイ ブルーは、トラピストビールの中でも特に重厚で複雑な香味を持つダークエール。冷やしすぎると香りが閉じ、温度が高すぎるとアルコール感が前に出るため、10〜14℃が最もバランスよく楽しめる温度帯です。
おすすめのマリアージュ
●ブルーチーズ(特にロックフォール)
濃厚な塩味と青カビの刺激を、ビールの甘味と熟成香が包み込み、驚くほど調和します。王道の組み合わせ。
● ビーフシチューや赤ワイン煮込み
深いコクと甘味が、シメイ ブルーのモルト感と完璧にリンクします。冬の食卓に最適。
● ダークチョコレート(カカオ70%以上)
ビールのカラメル香とチョコのビター感が重なり、デザートペアリングとして秀逸。
● 和食なら:すき焼き
割り下の甘辛さと卵のまろやかさが、シメイ ブルーの甘味・旨味と驚くほど相性が良いです。
▶スモークモン修道院のこと
ベルギー南部のワロン地域、シメイの郊外に位置する「ノートルダム・ドゥ・スクールモン修道院」は、世界的に有名なトラピストビール「シメイ」の発祥地です。1862年、カトリックの厳格な修道会であるトラピスト会の修道士たちによって創設され、以来、祈りと労働を軸とした修道生活の一環としてビール造りが始まりました。
「スクールモン修道院」は、ドイツ・フランス・ルクセンブルクにまたがるアルデンヌ高原の静かな森に囲まれた場所にあり、自然と調和した環境の中で修道士たちは質素で厳かな生活を送っています。修道院の敷地内には日本もみじが植えられ、訪れる人々に静寂と美しさを感じさせる空間が広がっています。
この修道院で造られる「シメイ」は、国際トラピスト協会によって認定された「本物のトラピストビール」のひとつです。その条件は、修道院内で醸造され、修道士が生産に関与し、収益が修道院の維持や社会貢献活動に使われること。スクールモン修道院はこれらを厳格に守りながら、伝統的なレシピと技術を継承しています。
ビール造りには、修道院内で汲まれる清らかな井戸水が使用され、麦芽やホップ、酵母などの原料は厳選されたもののみを使用。醸造後の麦芽かすは、修道院で製造される「シメイ・チーズ」を作る牛の飼料として再利用されるなど、持続可能な循環も意識されています。
「シメイ ブルー」をはじめとするシメイビールは、瓶内二次発酵によって熟成が進み、時間とともに味わいが変化するのが特徴です。発酵を終えたビールは、修道院から約12km離れた瓶詰め工場に運ばれ、1時間に4万本のペースで瓶詰めされます。その後、3週間ほどの再発酵期間を経て、世界中の愛好家のもとへ届けられます。
「スクールモン修道院」のビール造りは、単なる製造ではなく、祈りと精神性、そして地域社会への貢献が融合した文化的営みです。その静謐な空間と、修道士たちの誠実な手仕事が生み出す「シメイ」は、まさに魂のこもった一杯と言えるでしょう。
▶「スモークモン修道院」の歴史(年表)
1850年:
トラピスト会の修道士たちがベルギー・シメイ近郊のスクールモン高原に移住。荒れ地を開墾(※2)し、修道院の基礎を築く。
⇒荒れ地を開墾(※2)
〇スクールモン高原は、かつて農業に不向きな荒れ地でした。1850年、トラピスト会の修道士たちはこの地に移住し、祈りと労働を軸に開墾を開始。彼らは土地を耕し、畜産や農業を始め、やがて修道院を建設しました。この「荒れ地を聖地に変えた」という物語は、修道士の精神性と勤勉さを象徴する逸話として語り継がれています。
1852年:
正式に「ノートルダム・ドゥ・スクールモン修道院(Abbaye Notre-Dame de Scourmont)」として設立。祈りと労働を中心とした修道生活が始まる。
1862年:
修道院内でビール醸造が開始(※3)される。これが「シメイ」ブランドの起源となる。初期のビールは修道士の自給用だった。
⇒修道院内でビール醸造が開始(※3)
〇修道院でのビール造りは、もともと修道士たちの自給用として始まりました。外部販売を目的としたものではなく、修道生活の一部として位置づけられていたのです。やがてその品質が評判となり、地域社会への提供が始まり、現在の「シメイ」ブランドへと発展しました。
1876年:
修道院の敷地内でチーズ製造も開始。ビールとチーズの両方が地域経済に貢献するようになる。
1948年:
現在の「シメイ ブルー(Chimay Bleue)」のレシピが完成。クリスマス向けの特別醸造として登場し、後に定番商品となる。
1996年:
スクールモン修道院のビールが国際トラピスト協会によって正式に「トラピストビール」として認定される。
2005年以降:
環境への配慮や持続可能な生産体制が強化され、麦芽かすの再利用やエネルギー効率の改善が進む。
現在:
修道院は祈りと労働の伝統を守りながら、世界中に「シメイ」ブランドを展開。ビール、チーズともに高品質な修道院製品として評価されている。
Data
製造元:スモークモン修道院
スタイル: トラピスト(上面発酵)
原料: 麦芽、糖類、スターチ、オレンジピール、ホップ
アルコール度数: 9.0%
内容量:330ml、750ml、1,500ml、3,000ml、6,000ml
【広告】楽天/ビール通販
【広告】Amazon/ビール通販
・ご指定以外の商品も表示されます。
・お酒は二十歳になってから。
シメイ ホワイト
Chimay White
2026.01.01
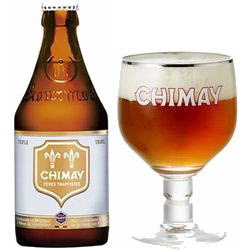
スパイス香るベルギー伝統ホワイトビール
『シメイ ホワイト』は、ベルギーのトラピスト修道院で造られる伝統的なベルジャン・ホワイトエールです。淡い黄金色の液色に、きめ細かな泡が立ち上がり、グラスに注いだ瞬間からスパイスと柑橘を思わせる華やかな香りが広がります。ホップの苦味は控えめで、コリアンダーやホワイトペッパーのようなスパイシーさが心地よく、軽やかな酸味が全体を引き締めています。口当たりは爽やかでありながら、修道院醸造ならではの奥行きとコクが感じられ、飲み進めるほどに複雑な余韻が現れます。食事との相性も良く、白身魚やチーズ、ハーブを使った料理と合わせると、その繊細な香味が一層引き立ちます。伝統と技巧が息づく、気品あるホワイトエールです。
■飲み方あれこれ!!
おすすめ温度:8〜12℃
冷やしすぎず、常温よりは少し低い“中温帯”が最も魅力を引き出します。
おすすめのマリアージュ
● 白身魚のカルパッチョ
柑橘の香りと軽い酸味が、魚の繊細な旨味を引き立てます。
● 山羊乳チーズ(シェーブル)
シメイ ホワイトのスパイシーさと酸味が、シェーブルの爽やかな酸味と好相性。
● ハーブを使った鶏料理
ローズマリーやタイムを使ったローストチキンは、ビールのスパイス感と美しく調和します。
● 和食なら:天ぷら(特に白身魚・野菜)
油の軽さと素材の甘みを、ビールの爽快感とスパイス香がすっきりまとめてくれます。
Data
スタイル: トラピスト(上面発酵)
原料: 大麦麦芽、小麦麦芽、ホップ、糖類
アルコール度数: 8.0%
内容量:330ml、750ml
【広告】楽天/ビール通販
【広告】Amazon/ビール通販
・ご指定以外の商品も表示されます。
・お酒は二十歳になってから。
シメイ レッド
Chimay Rouge
2026.01.01

カラメル香が広がる芳醇なダークエール
『シメイ レッド』は、ベルギーのスクールモン修道院で造られるトラピストビールの原点ともいえるダブルスタイルのエールです。深みのある赤褐色の液色に、カラメルモルト由来の甘やかな香りが立ち上がり、プルーンやレーズンを思わせる熟成感のあるアロマが続きます。口に含むと、柔らかな甘味とほのかな苦味が調和し、スパイスのニュアンスが奥行きを与えます。アルコール度数は高めながら、角の取れたまろやかな飲み口で、ゆっくりと味わうほどに複雑な余韻が広がります。食事との相性も良く、肉料理やチーズ、煮込み料理などと合わせると、その豊かなコクが一層引き立ちます。伝統と熟成の魅力が詰まった、気品あるダークエールです。
■飲み方あれこれ!!
●おすすめ温度:10〜12℃
複数の情報源で「10〜12℃」が最適とされており、いわゆる“セラー温度”が最も香味のバランスを引き出します。
おすすめのマリアージュ
●カマンベールやウォッシュタイプのチーズ
シメイ公式のチーズペアリングでも、レッドはクリーミーなチーズと好相性とされています。まろやかな脂肪分が、ビールの甘味とスパイス感を引き立てます。
●ローストポークや鴨のロースト
肉の旨味とカラメルモルトの甘味が重なり、余韻が深まります。
●ビーフシチューや煮込み料理
甘味とコクのある料理と合わせると、ビールの熟成感がより豊かに感じられます。
●きのこ料理(ソテー、クリーム煮)
シメイ レッドの土っぽいニュアンスと、きのこの旨味が美しく調和します。
●和食なら:照り焼き・すき焼き
甘辛いタレとビールのカラメル香が驚くほどマッチします。
Data
スタイル: トラピスト(上面発酵)
原料: 大麦麦芽、小麦麦芽、ホップ、糖類
アルコール度数: 7.0%
内容量:330ml、750ml(瓶)
【広告】楽天/ビール通販
【広告】Amazon/ビール通販
・ご指定以外の商品も表示されます。
・お酒は二十歳になってから。